
こんにちは、管理人のエディコです
みなさん、上司へ報告できていますか?
報告は、報・連・相(報告・連絡・相談)の一つでもあり、公務員を含むサラリーマンの義務と言っても過言ではない必須スキルです。
国民の三大義務である教育・勤労・納税に並ぶくらい重要だと思います。
それくらい重要な報告という行為ですが、ADHDにとっては苦手分野です。
今回はADHDが苦手とする理由とその克服方法をお伝えします。
✔上司への報告が苦手
✔報告の重要性がわからない
✔職場でのコミュニケーションに悩んでいる
Contents
報告の目的
まず、報告の目的から説明します。
問題の共有のため
 公務員は係員それぞれが全く別々の仕事をしていることが多いですが、少なくとも係長とはあなた自身の業務について情報を共有しておく必要があります。
公務員は係員それぞれが全く別々の仕事をしていることが多いですが、少なくとも係長とはあなた自身の業務について情報を共有しておく必要があります。
ミスやトラブルが特に発生していない状況でも、業務の進捗やこの先の方針など情報共有の精度が高まれば、チームとしての成熟度も高まります。
上司を安心させるため
「上司」の安心が目的というと、個人的な感じがして訝しく思われるかもしれません。
しかしながら、チームの精神衛生向上は巡り巡って、あなたのためでもあります。
あなたが報告を適切にしていなかったらどうなるでしょうか。
上司からすれば、報告をもらっていない業務の状況把握については、自分が見聞きした情報しかない状態で、ほとんどが未知の状態です。
報告がない状態は、あなたの中で仕事をとどめている状態です。
残念ながらこれでは、仕事をしていないのと同じです。
今すぐに上司に、進捗報告だけでもいいです。
報告の第一歩を踏み出しましょう。
安心感を与えてくれる人になる
 上司だって人間です。
上司だって人間です。
ただでさえストレスの溜まる職場では安心感というものに触れていたいです。
あなたは報告で安心を与えましょう。
上司にとって、安心感を与えてくれる人になりましょう。
少しずつでも良いですから上司の信頼を築いていきましょう。
報告の習慣で役所人生が変わる!?
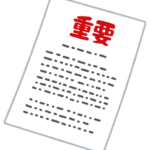 信頼されるようになると重要度が高い仕事を任せたくなるものです。
信頼されるようになると重要度が高い仕事を任せたくなるものです。
公務員は、重要度が高い仕事をしてもしなくても給料はさほど変わりません。
しかし、重要な仕事に携わることで、自己肯定感が高まり、仕事人生が充実していきます。
酸いも甘いも味わうことで、経験が豊富になり、厚みのある人間になります。
やや飛躍的な話ですが、報告の習慣が身につけば、基本的には役所人生が上向きになります。
ADHD報告「苦手」説
冒頭でお伝えしました通り、ADHDは報告が苦手だと思います。
その要因を3つ列挙していきます。
1.自分本位な報告
 相手の心理を読み取ることが苦手なADHDは、ついつい自分本位で話を進めがちです。
相手の心理を読み取ることが苦手なADHDは、ついつい自分本位で話を進めがちです。
報告に、自分の主観が混じることや、予測の範疇を超えた空想を盛り込んでしまうこともあります。
シンプルな話が複雑化したり、誇大な話になったしまい、報告の受け手を混乱させます。
また、相手の心情を汲み取ってあげることも苦手です。
明らかに相手が忙しい、機嫌が悪いことを気にも留めず話しかけてしまった経験はありませんか?
ADHDは、対人関係での成功体験の絶対数が少ない傾向にあります。
そのため、報告にあたり、二の足を踏んでしまったり、身構えて必要以上に肩の力が入るなど、悪循環が起こっている場合があります。
2.話がまとまらない
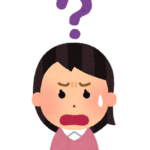 ADHDの話し方の特徴として、衝動的に言いたいことを言ってしまう傾向があります。
ADHDの話し方の特徴として、衝動的に言いたいことを言ってしまう傾向があります。
また、自分が特に伝えたいけど、客観的にはあまり重要ではない部分を伝えることに固執してしまうこともあります。
伝えるべき重要なことよりも、苦労したこと、面白かったことを優先して伝えてしまったことはありませんか?
状況にマッチすれば、最高の話者になれる可能性を秘めているADHDです。
しかし、場面が仕事の報告という堅いシチュエーションでは、基本的にはその武器を活かせません。
3.先延ばし癖
ADHDは先延ばし癖により、報告の適期を逃してしまう傾向にあります。
すぐにやるべき仕事が目の前にあるのに、気づいたらいつでもできる些細な仕事に手を付け始めてしまっていることはないでしょうか?
やるべき仕事に取り掛かることは非常にストレスがかかります。
ADHDは特にそのストレスへの耐性が低いようです。
仕事に取り掛かるストレスから逃れるために、原因となっている仕事から目を反らしつつ、仕事をしている姿勢を保つため、別の仕事に手を付けます。
これがADHDの先延ばしのメカニズムです。
報告のタイミングまで先延ばしにしていませんか?
報告は内容や伝え方よりも、タイミングが重要です。
どんなに良い報告でもタイミングを逃してしまえば、受け手を不快にさせてしまうこともあります。
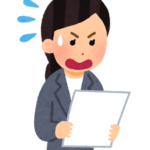 また、先延ばしをすると仕事の難易度があがります。
また、先延ばしをすると仕事の難易度があがります。
簡単に完結できた仕事なのに、放置したことによって物凄い労力がかかることがあります。
先延ばしによって解決できる仕事はありません。
今回の記事で一番伝えたかったことがこれだったりします。
報告『苦手』の克服法
ADHD報告「苦手」説には共感できる部分、そうでない部分があったかもしれませんが、それらを克服する方法も紹介します。
克服法①:すぐに報告する
 上司へ報告するベストタイミングは即時です。
上司へ報告するベストタイミングは即時です。
それを逃すと、上司の仕事が落ち着いている時など、タイミングを窺う必要があります。
空気を読むことが苦手なら、即時のタイミングで報告を狙っていきましょう。
その際に、「取り急ぎ報告です」と頭につけてみましょう。
こうすることで、話が完全にまとまっていなくても、情報の鮮度を優先しました感が出て、ハードルが少し下がります。
また、報告の受け手側も、「これから報告が来る」とわかるので、報告を受けるモードになります。
注意点
いくら急ぎの報告でも、情報の正確さだけは欠かさないようにしましょう。
報告の前に事実確認など、情報の裏どりは必ずやりましょう。
また、話す内容や順序を一度書き出ししておくと、まとまりのある報告ができます。
克服法②:事実ベースで話す
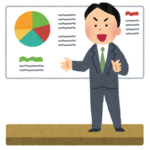 報告は、シンプルにありのままに話しましょう。
報告は、シンプルにありのままに話しましょう。
印象や感覚、感想といった曖昧なものをそぎ落とします。
あなたの主観はいったん置いておいて代わりに、受け取った書類、現場写真、過去のデータ、製品カタログなど、正確さが客観的に担保されているもの、つまり事実を用意しましょう。
むしろ、報告に事実以外はいらないです。
注意点
事実以外はいらないと言いましたが、意見や予測など、自分なりの考えは備えておきましょう。
聞かれれば答えるというスタンスで十分です。
報告の受け手が判断に迷ったとき、現場を知っている人の直感を聞いてみたくなるものです。
克服法③:こまめに報告する
部下が引き起こした業務上のトラブル処理やミスへの対処は、上司の仕事に含まれると考えるのが一般的です。
ただし、事前に問題共有を怠っていなかった場合に限ります。
報告をしていなかったために防げなかったトラブルはさすがに上司に責任はないと思います。
(理不尽な話ですが、実際にはそれでも上司の責任にはなります。)
上司への報告はセーブポイント
 唐突ですが、あなたはRPGなどのゲームはしますか?
唐突ですが、あなたはRPGなどのゲームはしますか?
上司への報告はセーブポイントだと思いましょう。
ボス戦前は無駄にセーブ頻度が増えたりしますよね。
同じように仕事の重要な局面では、報告の頻度も増やしていきましょう。
もしも、トラブルが発生しても、そこまでは上司にも責任があります。
ちょっとずるく感じるかもしれませんが、上司とっても理不尽に責任を負わされるよりは納得がいくと思います。
まとめ
今回はADHD報告「苦手」説の克服法を3つ紹介しました。
ADHD報告「苦手」説の克服法
- ①すぐに報告する…報告のベストタイミングは即時です。ただし、事実確認は怠らないようにしましょう。
- ②事実ベースで話す…報告は客観的な事実を伝えましょう。ただし、あなたなりの意見がいらないという意味ではありません。
- ③こまめに報告する…報告の頻度を増やしていきましょう。報告はセーブポイントです。
これらの方法が全ての状況に当てはまるとは限りません。
テクニックの一つとして捉えてください。
また、上司のタイプも様々です。
場合によっては逆効果になる可能性がありますので、予めご了承ください。
漠然とした不安は「認知のゆがみ」に由来するものかもしれません
仕事や人間関係のちょっとしたことで、不安になったり、悩んだり、イライラしてしまうのは「認知のゆがみ」によるものかもしれません。「認知のゆがみ」とは?
同じ状況や出来事に遭遇しても、事実として得られるものは、それぞれの人の認知の仕方によって異なります。出来事の受け止め方が人によって違うために、それに伴う感情や行動も、時として他人に理解されなかったり、常識外れとされてしまったりすることがあります。
例えば、上司に仕事のミスを指摘された場合、
「再発防止策を考えよう」「上司がいてくれてよかった」と前向き捉える人もいれば、
「こんなミスしてしまうなんて自分はなんてダメな人間なんだ」と落ち込んだり、
「この程度のミスを指摘するなんて、上司は器の小さな人だ」と敵意を持って捉える人もいます。
同じ出来事なのに、捉え方ひとつでこのように気持ちの違いが生まれてしまいます。
認知のゆがみとは、一般的に、同じ出来事に遭遇した際に、歪んだ捉え方をすることで、自分の気持ちが不安になったりイライラしたり、ネガティブなものになることを指します。
「認知のゆがみ」無料診断
認知の仕方には正解がなく、ポジティブなら良いというわけでもありません。けれども、必要以上にネガティブに受け止めて、その感情を蓄積させてしまっても人生が楽しくありません。
自分自身の認知のクセを知って、コントロールできればベターだと思います。
下のバナーから、「認知のゆがみ」の無料診断ができます。
無料診断だけなら会員登録も不要ですのでお試しください。

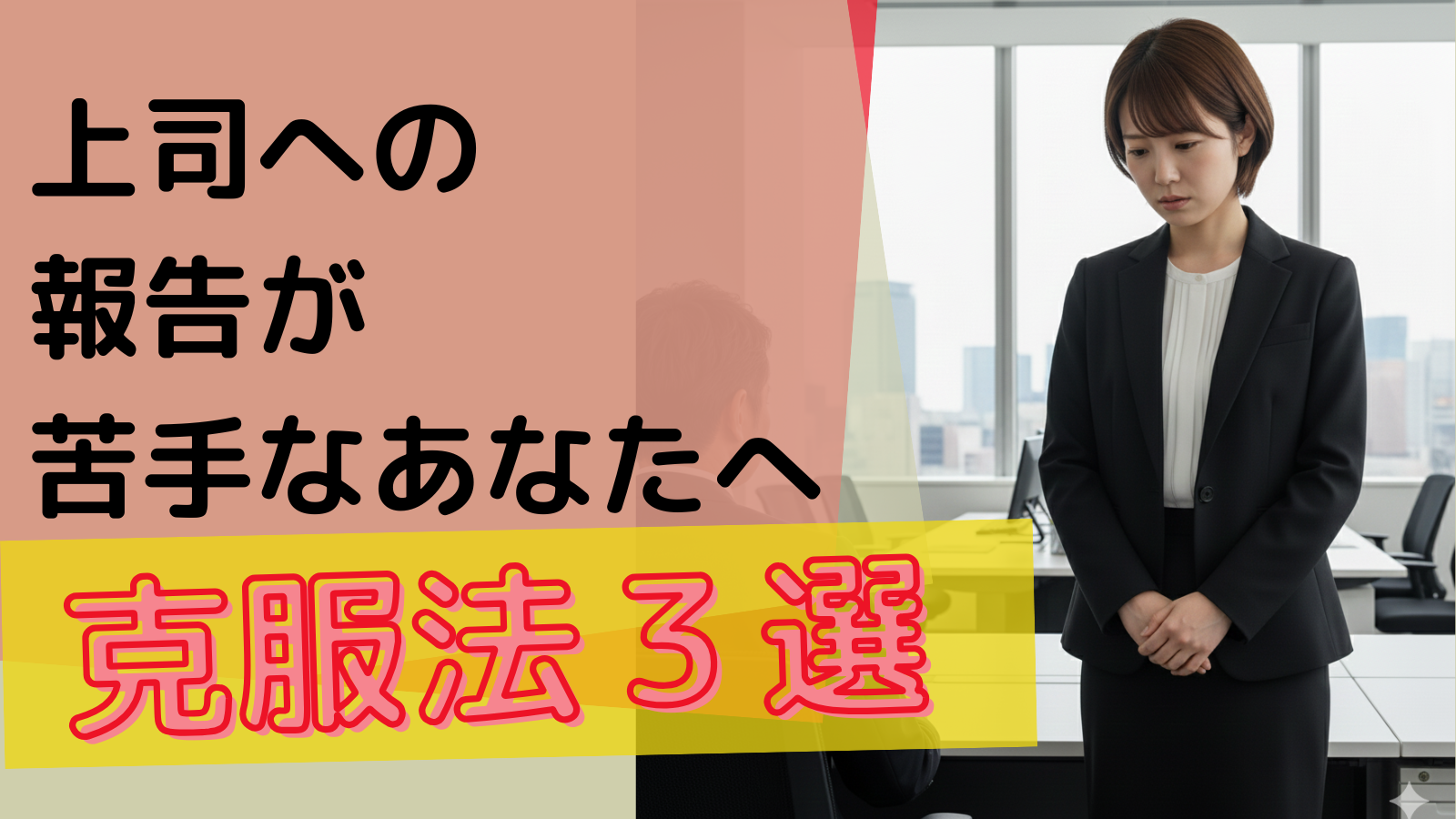



コメント