ネットを見ていても「ADHDは公務員に向いているか?」の疑問を多く見かけます。
ここでは私なりの考えを述べます。
なお、ここでいう「公務員像」も「ADHD像」も一般論と私の了見によるものです。
全ての人に当てはまるわけではないことに注意してください。
✔役所で働いていく自信がなくなってきた
✔役所で働く現役・地方公務員の実情が知りたい
Contents
ADHDは公務員に向いているのか?
ADHDの人は公務員に向いていません。
これは一般論ですし、ADHDを抱えながら公務員を15年以上経験してきた私がたどり着いた結論でもあります。
・公務員はガンジガラメ
公務員人生は法律に基づいて就職し、法律に基づいて働き、法律に基づき退職します。
さらには退職後も守秘義務が求められ、公務員になるということは法律に心臓を捧げるようなものです。
加えて古い体質の組織が多く、上下関係などの不文律も豊富です。
・ルールはADHDの天敵?
不注意、多動・衝動性から行動の抑制が効きにくいADHDにとっては厳しいルールを守ることは苦手分野であり、強いストレスになります。
ただし、ADHDは人それぞれの特性を持っています。
ルールを守ること・守らせることに強い関心も持つタイプのADHDはこの限りではない可能性があります。
公務員の仕事はADHDの苦手要素が詰まっている
・定型の仕事が中心
・決まったことを決まった通りに
・文書は正確に
・誰にでも平等に
マイペースで飽きっぽい人が多いADHDには厳しいかもしれません。
・ワンオペ事業が多い
これは民間でも言えることですが、公務員も人手不足で一人当たりの業務量が多いです。
それ故に直属の上司も把握していない業務を係員が抱えていることがあります。
さらに隣の席の係員が何をやっているかは把握できても、内容・進捗まではわかっていない業務が多くあります。
人数に対して業務が多いので、仕方ない部分はありますが、計画性・進捗管理を自分一人でやらなければなりません。
ADHDは、興味のあることには破竹の勢いで取り組めるのですが、興味のないことは先延ばす傾向にあるので、事業が進んでいないことによるトラブルを起こしがちです。
ADHDは公務員に絶対に向いていない?
デメリットばかり紹介しましたが、メリットもあります。
とはいえ、必ずしも良い点ともいいきれないものです。
これをもって「向いている」ととらえるかはみなさん自身で判断してください。
・クビがない
公務員には、いわゆる解雇がありません。
懲戒免職はありますが、21日間正当な理由なく欠勤や横領など、よっぽどのことがない限り適用されません。
そのためか、公務員にはADHDをはじめとした発達障害グレーの人が多いといわれています。
(私の主観で数字などの根拠がないです。すみません。)
・給与水準が良い
地方によってばらつきはありますが、地方公務員の平均年収は500~600万円とされています。
初任給は安いですが、成績により伸び率に差があるものの、年功序列で昇給します。
ADHDが向いているとされるクリエイターよりも給与水準は良いです。
| 地方公務員 | 500~600万円 |
| Webデザイナー | 340万円 |
| グラフィックデザイナー、イラストレーター | 330万円 |
| クリエイティブディレクター、アートディレクター | 467万円 |
| 映像エディター | 336万円 |
| 工業デザイナー | 336万円 |
| イベント、芸能関連 | 376万円 |
出典:DODA平均年収ランキング2015より
・アイディアが活かせる
地方では特に、少子高齢化・過疎化が進んでいて、今までにない問題に直面しています。
自治体の存続に待ったなしの状況の中で、ADHDの突飛なアイディアが自治体を救うことがあるかもしれません。
ただし、企画系の業務に就いている職員は各役所でもほんの数名で、それらの職員も平時は事務作業を行っているのが現実です。
漠然とした不安は「認知のゆがみ」に由来するものかもしれません
仕事や人間関係のちょっとしたことで、不安になったり、悩んだり、イライラしてしまうのは「認知のゆがみ」によるものかもしれません。「認知のゆがみ」とは?
同じ状況や出来事に遭遇しても、事実として得られるものは、それぞれの人の認知の仕方によって異なります。出来事の受け止め方が人によって違うために、それに伴う感情や行動も、時として他人に理解されなかったり、常識外れとされてしまったりすることがあります。
例えば、上司に仕事のミスを指摘された場合、
「再発防止策を考えよう」「上司がいてくれてよかった」と前向き捉える人もいれば、
「こんなミスしてしまうなんて自分はなんてダメな人間なんだ」と落ち込んだり、
「この程度のミスを指摘するなんて、上司は器の小さな人だ」と敵意を持って捉える人もいます。
同じ出来事なのに、捉え方ひとつでこのように気持ちの違いが生まれてしまいます。
認知のゆがみとは、一般的に、同じ出来事に遭遇した際に、歪んだ捉え方をすることで、自分の気持ちが不安になったりイライラしたり、ネガティブなものになることを指します。
「認知のゆがみ」無料診断
認知の仕方には正解がなく、ポジティブなら良いというわけでもありません。けれども、必要以上にネガティブに受け止めて、その感情を蓄積させてしまっても人生が楽しくありません。
自分自身の認知のクセを知って、コントロールできればベターだと思います。
下のバナーから、「認知のゆがみ」の無料診断ができます。
無料診断だけなら会員登録も不要ですのでお試しください。


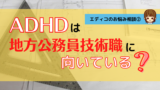


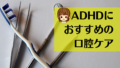
コメント